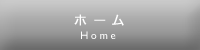IPGのサービス、Gガイド、Gガイドモバイル、シンジケーティッドGガイド、Gガイド for Wii、G-Guide for windows
地デジ、ワンセグ、電子番組表…<放送と通信の連携>が叫ばれる中、「テレビをもっと楽しくする」ためのさまざまな新メディア、新ツールが登場している。では、本当にテレビは「もっと楽しく」なるのだろうか。メディアやツールがどんなに革新されても、視聴者を笑わせたりホッとさせたり感動させたりするのは、そこで放映される番組というソフトにほかならない。<放送と通信の連携>というハードの革新は、番組というソフトをどう変えていくのか、あるいは変えていかないのか―その答えを、数多くのヒット番組を手がけてきた、第2日本テレビ事業本部・土屋敏男エグゼクティブディレクターにうかがってみました。
―<放送と通信の連携>みたいなことが言われてきた今、番組の作り手として、何か「変化」みたいなものを感じたりしますか?
テレビの使命といった本質的なものは変わりません。でも、その手前の現象としてはいろいろな変化が起きていますよね。そのひとつが<通信>というものが出てきたことによって「番組視聴に国境がなくなった」ことです。ご存知のように、「You Tube」のようなサイトのようなサイトに大勢の日本人がアクセスしている時代です。これは何を意味するかというと、ソフトさえ面白ければ、それを流すハードがどの国の何というチャネルかはどうでもいい時代になった、ということです。
―となると、「日本のテレビ番組の国際競争力」みたいなことも、いずれ問われてくるのでしょうか?
私は、日本のテレビ番組は、世界のレベルから見ても「クオリティが高い」「面白い」と思っています。その背景のひとつに、ハード提供者とソフト提供者が一緒であるという日本特有の事情があります。日本は、放送免許を持っているテレビ局が番組も企画するわけで、ハード提供者とソフト提供者が切り離されたアメリカとは大きく違います。言い換えれば、日本のテレビ番組は、テレビ局という箱に保護され育まれてきたわけであり、そのぶん高いクオリティを維持してこられたといえます。
―「テレビ局という箱に保護されてきた」とは?
平たく言うと、番組づくりに「失敗もある程度許される」という<あそび>が生まれるということ。この<あそび>が、クリエーティブな世界には非常に重要なのです。たとえば、アメリカの場合、番組企画会社は常に「放送会社に採用してもらいやすい」コンテンツを提供せざるをえません。なぜなら、採用されなければ食べていけないから。そうなると、実験的なものはどんどんできにくくなります。ところが、日本の場合、放送会社と番組企画会社が同じなので、そういう<あそび>がある程度許されたわけ。そこから、次の時代のヒット番組が生まれたりするのです。
―放送と通信が連携することで、そういう<あそび>が新たに生まれる可能性はあるでのでしょうか。
十分ありますね。テレビ番組というのは、人の心を動かしてなんぼ。―この点に関しては、放送も通信も何も違いません。方法論の違いだけです。ただ、この「方法論の違い」で、コンテンツの作り方が違ってきます。たとえば、「お笑い」というジャンルを例にとっていえば、<放送>が提供する笑いは、「みんなが笑える笑い」、言い換えれば「浅くてもいいから広い笑い」。放送はマスを対象としたメディアですから。一方<通信>が提供する笑いは、「わかる人だけが笑える笑い」、言い換えれば「狭くてもいいから深い笑い」でいい。<通信>は個を対象としたメディアですから。この後者の例として、この間私が第2日テレでやった松本人志のコントがあります。これは、完全に「わかる人だけに笑ってもらえればいい」コント。ここまで作家性の強いコントは、いままでのテレビでは絶対にできません。
―それって、私たちGガイドが目指している「テレビの視聴体験を豊かにする」ことと通じるものがありますね。
そうです。いままでは「それは、視聴率取れないからナシだった番組が「それもアリだね」となるわけだから、視聴者にとっては選択が拡がるし、作り手に<あそび>が増える。また、タレントの側にとっても、いままでは「マスで数字が取れる芸人」だけが彼らのゴールだったけど、「そうじゃない道もあり」となるわけ。つまり、テレビ番組の作り手も、受け手も、さらには演じ手も、みんなが「豊か」になる。そういうことを実現するのが、公共の電波を流す企業の使命だと私は思います。
―ということは、作り手にとって、<放送と通信の連携>は歓迎すべきことなわけですね。
私は、そう思います。<通信>の登場によって、いままでのテレビでは実現できなかったコンテンツを実現できる可能性が出てくるわけですから。逆に、そこで<放送>の縮小版みたいなことやったら、まったく意味ないと思います。