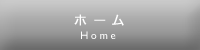IPGのサービス、Gガイド、Gガイドモバイル、シンジケーティッドGガイド、Gガイド for Wii、G-Guide for windows
2006.March | vol.35

ワンセグ時代。「通信」と「放送」は、どうコラボレートしていくのか。
KDDI株式会社
メディア本部メディアビジネス部 クロスメディアグループリーダー
家中 仁 さん
ワンセグ放送が始まる。携帯電話でTV番組(電子番組表)が見られ、そのまま目の前のTVのリモコンにもなる。ついに、そんな時代がやってきました。数年前から言われつづけてきた<通信と放送の融合>という潮流。今年、その大きな第一波が、押しよせます。通信は、放送とどんなコラボレーションを期待、想定しているのか―『着うた(R)』をはじめ、キラーコンテンツを次々と世に送り出し、若い世代からの絶大な支持を獲得してきた<au>。そのブランドを築き、支えてきた<KDDIの頭脳>にきいてみました。
-<放送と追伸の連携>に関して、KDDIさんでは、今までどんな取り組みをしてきましたか。
2003年に、auでは『EZ・FM』というサービスを始めました。これは、単純に携帯電話にFMラジオが付いたというだけではなく、通信を使ってオンエア楽曲の曲名やアーティスト名も確認できる機能が付いており、まさに、放送と通信が連携し、ひとつの<文化>を創ることができた最初の典型事例と言えるのではないでしょうか。この『着うた(R)』を足がかりに、今ではさまざまな通信放送連携の事例が生まれています。たとえば、テレビ朝日の『ミュージックステーション』というテレビ番組で<着うた(R)ランキング>が紹介されているのですが、オンエアされたとたんに、『着うた(R)』検索のアクセス数がグーンと上がるんです。つまり、視聴者は、テレビと携帯と、同時に見ているわけです。テレビで情報をとり、同時に携帯で調べたり体験したりする…私たちは<ダブルウィンドウ>と呼んだりしているのですが、そういうライフスタイルが、すでに若い世代の人たちを中心にあたりまえのものになりつつあること。つまり、放送と通信の連携が、すえに実生活化しているということです。
―ワンセグ放送の開始を契機に、テレビと携帯電話のコラボレーションということが世の中では話題になっていますが、KDDIでは、そのあたりどうお考えですか?
先ほども申し上げましたとおり、<テレビで情報をとり、携帯で調べたり体験したりする>というスタイルが、今のユーザーにとっては最も自然なふるまいなのではないでしょうか。テレビと携帯電話とでは、前提となる視聴態度が違うわけですから。よく言われることですが、テレビは、わりと漫然とみがちな受動的視聴メディアであるのに対して、携帯電話は、わりと明解な意思・意図をもって見る能動的視聴メディアです。テレビからはランダムに大量の情報が入ってくる。その中から、自分が興味のある情報について、詳しく調べたり体験したりするツールが携帯電話なわけです。
―今回、auのコンテンツに、弊社(IPG)が提供する電子番組表サービス『Gガイドモバイル』を入れていただいた意図は、どのようなところにあるのでしょうか?
テレビ番組表というのは見たい番組を探すという主体的なコンテンツですから、携帯電話という主体的な視聴メディアのユーザーニーズにとても合っていると思い舞うs。単純に考えて、携帯電話の中にテレビ番組表が入っていれば、帰りの電車の中で、今夜何やってるかなぁ…と思って見るでしょう。私たちの仕事のミッションとしては、ユーザーの携帯電話との接触時間を1分、1秒でも長くして、その中でたくさんのコンテンツを見つけ、楽しんでもらうことです。その意味では、御社の提供する『Gガイドモバイル』は、私たちにとって素晴らしいコンテンツだと思っています。
―ユーザーの携帯電話との接触時間が1秒でも長くなれば、そのぶん、携帯電話のメディア価値が上がる、そうなれば、広告メディアの価値としても上がるだろう、ということですね。
おっしゃるとおりです。いま日本では、KDDIグループだけでも約2,500万台、全市場合わせて約9,000万台の携帯電話が使われています。また、携帯電話には、様々な機能が搭載され、そのうえで様々なコンテンツが提供されることにより接触時間もますます長くなってきています。しかも、年齢や性別毎にセグメントした情報発信も可能です。つまり。広告メディアとしては<とてつもない価値>を持っているわけです。しかし、今のところ、この携帯電話を広告メディアとしてフルに活用するビジネスモデルは開発されていません。これは、私たちKDDIだけではできないことであり、広告ビジネスモデルを知り尽くした広告代理店のブレーンが必要なのです。<放送と通信の連携>というメディアコラボレーションは、<広告コンテンツと通信コンテンツの連携>という別レイヤーのコラボレーションを生み出すということです。その意味で、電通、ジェムスター、東京ニュース通信社が出資してつくられた御社のような会社には、ぜひ新しいビジネススキームを創造してほしい、と大いに期待しています。
―ありがとうございます。頑張ります。これからも、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそ、どうぞよろしくお願いします。